 悩む人
悩む人医者は激務、ブラックすぎるのが基本?
人によって全然違うという話は本当なの?
「医者は激務すぎてブラックだ」と言われることが多いですが、実際のところ、その働き方は一律ではありません。確かに救急科や外科のように長時間労働が当たり前の診療科もありますが、皮膚科や眼科、健診センターなどでは比較的規則的な勤務が可能なケースもあります。
また、勤務先によっても違いがあり、大学病院では研究や教育業務が加わる一方、民間病院やクリニックでは負担が軽減されることもあります。
このように「医者は激務」というのは一概には言えず、どの診療科を選ぶか、どの職場で働くかによって大きく異なります。本記事では、医師の労働環境がなぜ「ブラック」と言われるのか、そしてどのような条件なら比較的働きやすいのかについて詳しく解説します。今の医師としての働き方について疑問や悩みを持っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
\ 医師転職なら業界実績No.1! /
医者が激務/ブラックすぎると言われる理由/状況
まずは、医者が激務/ブラックすぎると言われる理由/状況について整理してみましょう。結論、それは以下の通り。
順番に詳しく説明しますね。
医者が激務/ブラックすぎると言われる理由/状況①:勤務時間が不規則で、夜勤や当直や長時間労働が常態化
医師の労働環境は、勤務時間の不規則さ、夜勤や当直の頻度、そして長時間労働が常態化していることが特徴です。これらの要素は、医師の健康や生活の質に大きな影響を及ぼします。特に、夜勤や当直は、昼夜逆転の生活を強いられるため、身体的・精神的な負担が増大しがち。さらに、長時間労働が続くことで、疲労が蓄積し、医療の質や安全性にも影響を及ぼす可能性があります。
このような状況を改善するために、政府は医師の時間外労働の上限規制を導入しました。具体的には、原則として月100時間未満、年間960時間以内とするA水準が設定されています。しかし、救急医療や専門研修など特定の状況下では、特例として年間1,860時間までの時間外労働が認められるB水準も存在します。これらの規制は、医師の過重労働を防ぎ、適切な労働環境を確保することを目的としています。
とはいえ、これらの上限規制が導入されても、医療現場の実情としては、依然として長時間労働が続いているケースも少なくありません。特に、地方の医療機関や人手不足の診療科では、医師一人ひとりの負担が大きくなりがち。このような状況を改善するためには、医師の労働環境の見直しや、医療従事者全体の働き方改革が必要とされているのが現状なのです。
医者が激務/ブラックすぎると言われる理由/状況②:人手不足により一人の医師に多くの業務が集中
医療現場では、慢性的な人手不足が問題となっています。特に地方や過疎地域では医師の確保が難しく、一人の医師に多くの業務が集中する状況が続いています。これにより、診療だけでなく事務作業や研究、研修指導なども担わなければならず、結果として過重労働につながります。
この問題の一因として、医療従事者の地域偏在や診療科ごとの偏りが挙げられます。例えば、都市部の病院には医師が比較的多く集まる一方で、地方の医療機関では必要な人員を確保できず、少ない医師で多くの患者に対応しなければなりません。
対策として、タスクシフティング(業務分担)を進め、看護師や医療事務スタッフと業務を分けることが求められています。また、オンライン診療の活用やICTの導入による業務効率化も重要です。医師の負担を軽減することで、医療の質向上にもつながることからこれらのことが現場では急務とされています。
医者が激務/ブラックすぎると言われる理由/状況③:クレームや訴訟リスクなど責任がつきまとう
医師は、患者の生命や健康を預かる立場であり、その責任は非常に重大です。しかし、医療行為においては、予期せぬ結果や合併症が生じることもあり、これが患者やその家族からのクレームや、場合によっては訴訟に発展するリスクを伴います。このような状況は、医師にとって大きな精神的負担となり、日々の診療に影響を及ぼす可能性があります。
実際に、医療訴訟の件数は増加傾向にあり、例えば株式会社メディウェルが行った医師1,632名へのアンケート結果によれば、多くの医師が訴訟リスクを感じていると報告されています。特に、診療科目によっては訴訟リスクの程度が異なり、内科や外科、産婦人科などでは高いリスクが指摘されています。このような状況下で、医師は常に最新の医療知識と技術を習得し、患者との信頼関係を構築することが常に求められます。
ワークライフバランスを重視した医者の働き方
冒頭でも述べたように、何も医者全部が激務でブラックすぎるということはありません。勿論、共通して大変な点があることは間違いないのですが、その労働環境としての過酷さはケースによってばらつきがあるのです。
ここからは、ワークライフバランスを重視した医者の働き方として現在注目されているものをいくつかピックアップして解説。
こちらも順番に見ていきましょう。
働き方①:健診・人間ドック専門の医師
健診や人間ドックを専門とする医師の働き方は、ワークライフバランスを重視する上で魅力的な選択肢の一つ。これらの業務は、主に健康診断や予防医療を担当し、患者の早期発見や健康維持に寄与します。
この分野の特徴として、勤務時間が規則的であり夜勤や当直がほとんどない点が挙げられます。多くの健診施設やクリニックでは、平日のみの勤務が一般的であり、土日祝日は休診となるケースが多いです。そのため、家族や友人との時間を確保しやすく、プライベートとの両立がしやすくなります。
また、健診業務は予約制が主流であり、1日のスケジュールが計画的に組まれています。これにより、突発的な業務が少なく、精神的な負担も軽減されます。さらに、患者の急変対応や緊急手術といった高ストレスの業務が少ないため、安定した労働環境が期待できます。
働き方②:産業医(企業勤務)
産業医として企業に勤務する医師の働き方も、ワークライフバランスを重視する上で有効な選択肢。
産業医は、企業内で従業員の健康管理や労働環境の改善を担当します。具体的な業務内容としては、定期健康診断の実施、職場の衛生環境のチェック、メンタルヘルス対策の提案などが挙げられます。これらの業務は、一般的に平日の日中に行われ、夜勤や当直はほとんどありません。ゆえに、規則的な生活リズムを維持しやすく、プライベートの時間を確保しやすい環境と言えるでしょう。
さらに、産業医は企業の就業規則に基づいて勤務するため、一般的なオフィスワーカーと同様の労働条件が適用されます。有給休暇や長期休暇の取得も比較的容易であり、家族との時間や自己啓発のための時間を持つことが可能です。また、企業内での健康教育や労働環境の改善提案を通じて、従業員の健康増進に直接貢献できる点も魅力です。
働き方③:クリニック(外来のみ)の医師
外来診療のみを行うクリニックでの勤務は、ワークライフバランスを重視する医師にとって適した働き方の一つです。これらのクリニックでは、入院患者を持たず、外来診療に特化しています。そのため、夜間の急変対応や当直業務がなく、勤務時間が安定していることが特徴です。
多くのクリニックでは、診療時間が決まっており、予約制を導入している場合が多いです。総じて1日のスケジュールが予測しやすく、プライベートの予定も立てやすい環境といえるでしょう。
また、外来診療は患者とのコミュニケーションが中心となり、長期的な関係性を築くことが可能。慢性疾患の管理や生活習慣病の予防指導など、患者の健康維持に寄与する役割を担います。これにより、医師としてのやりがいを感じながらも、過度な労働負荷を避けることも期待できます。
加えて、クリニック勤務は地域医療に密着しており、地域住民の健康相談や予防接種など、多岐にわたる業務を経験できます。これにより、医師としてのスキルを幅広く磨くことができ、キャリアの幅を広げる選択肢にもなるでしょう。
働き方④:特定の診療科の市中病院・民間病院
市中病院や民間病院の中でも、特定の診療科を選ぶことでワークライフバランスの取りやすさが大きく異なります。特に、皮膚科・眼科・精神科・整形外科(外来中心)などの診療科では、夜勤や緊急対応の頻度が低く、比較的安定した勤務が可能です。
例えば、眼科は外来診療中心であり、手術があったとしても計画的に行われるため、突発的な業務が少ないです。また、皮膚科も入院患者が少なく、外来診療が主流のため、規則的な勤務が期待できます。
一方、精神科は救急対応が少なく、急性期の患者対応を除けば、落ち着いた診療環境が整っていることが多いです。特に、慢性期の患者を主に診る病院では、業務負担が軽減され、医師の負担が抑えられます。
働き方⑤:大学病院の研究職(臨床から離れる)
大学病院の研究職は、臨床業務から離れ、研究や教育を主な業務とする働き方です。キャリアとして選択することで、臨床医としての夜勤や当直、緊急対応などの負担を軽減することが幾分か可能になります。
研究職では、基礎医学研究や臨床研究、論文執筆、学会発表などが主な業務。これらは、突発的な患者対応がないため、比較的自由なスケジュールで働くことができます。また、研究助成金や外部資金を活用することで、経済的な安定を確保しながら専門分野の研究に専念できる環境が整っています。
ただし、研究職は給与水準が臨床医に比べて低い場合があるため、キャリアの方向性を考慮する必要があります。また、研究成果が求められるため、一定のプレッシャーも伴うことは理解しておきましょう。
\ 医師転職なら業界実績No.1! /
【SNSの声】医者は激務?ブラックすぎ?
実際に医者は激務なのか?ブラックすぎ?という疑問についてSNSを中心に実際の声や意見を調査しました。
該当するものが複数見られたのでいくつかピックアップして確認していきましょう。
SNSの声①:何でこんなに医者って激務なんやろうな
何でこんなに医者って激務なんやろうな
— アンソニー (@ansonyforgf) February 25, 2025
気づいたら日回ってるからなあ、不思議や
何でこんなに医者って激務なんやろうな
気づいたら日回ってるからなあ、不思議や
SNSの声②:サボってる人間とこき使われてる人間の差が激しい
大学病院っていうのは医者全員が激務みたいなイメージだけど実態はサボってる人間とこき使われてる人間の差が激しいのが1番の問題で、それが雰囲気の悪さというか魔境度に拍車をかけてるんだよな
— メルデちゃん (@drunkokko) February 6, 2025
大学病院っていうのは医者全員が激務みたいなイメージだけど実態はサボってる人間とこき使われてる人間の差が激しいのが1番の問題で、それが雰囲気の悪さというか魔境度に拍車をかけてるんだよな
SNSの声③:まーじで医者は頭おかしい勤務体制
まーじで医者は頭おかしい勤務体制だよ。当直明けでオペや外来してんだもん。当直でほぼ寝てない外科医に切られてんだよ。研究日は他院に派遣されてんだもん。休み週1くらいしかないんだもん。オンコールだとそれもなし。
— まゆみん⊿ (@mayumin0818) August 17, 2023
まーじで医者は頭おかしい勤務体制だよ。当直明けでオペや外来してんだもん。当直でほぼ寝てない外科医に切られてんだよ。研究日は他院に派遣されてんだもん。休み週1くらいしかないんだもん。オンコールだとそれもなし。
SNSの声④:民間のハイポ病院で2000万ちょい稼ぐのが一番の勝ち筋
激務してる自分に酔ってる薄給大学病院勤務ハイパー科の医者を鼻で笑いながら民間のハイポ病院で2000万ちょい稼ぐのが一番の勝ち筋なんだよなあああああああああああ
— Пушистый (@HexenschuB) November 4, 2024
激務してる自分に酔ってる薄給大学病院勤務ハイパー科の医者を鼻で笑いながら民間のハイポ病院で2000万ちょい稼ぐのが一番の勝ち筋なんだよなあああああああああああ
SNSの声⑤:新卒で勤めた医院はブラックすぎて逃げ出すように辞めた
新卒で勤めた医院はブラックすぎて逃げ出すように辞めたけど、僕の超絶根暗ネガティヴを1からではなく本当に0から叩き直してくれた院長には感謝してる
— 町の勤務医 (@nk_dent) February 25, 2025
新卒で勤めた医院はブラックすぎて逃げ出すように辞めたけど、僕の超絶根暗ネガティヴを1からではなく本当に0から叩き直してくれた院長には感謝してる
【SNSの声】医者は激務?ブラックすぎ?:まとめ
- 何でこんなに医者って激務なんやろうな
- サボってる人間とこき使われてる人間の差が激しい
- まーじで医者は頭おかしい勤務体制
- 民間のハイポ病院で2000万ちょい稼ぐのが一番の勝ち筋
- 新卒で勤めた医院はブラックすぎて逃げ出すように辞めた
SNSの意見を見ると、医師の労働環境には大きな格差があり、「激務すぎる」と感じている人が多い一方で、比較的バランスの取れた働き方をしている医師もいることが分かります。
長時間労働や当直の多さ、不規則な勤務シフトに対する不満を表す声が複数確認できる一方で、同じ医療機関内でも負担の分配に偏りがあることがうかがえます。加えて、高収入を得ながら比較的穏やかな働き方を選ぶことが可能であることも伺えます。
結局のところ、医師の労働環境は勤務する病院や診療科によって大きく異なり、ブラックな職場もあれば、比較的働きやすい環境も存在します。医師として長く働くためには、職場の選択が極めて重要な要素となるでしょう。
医者の求人/転職市場について
医師の求人・転職市場は、近年、人材の流動性が高まり、常に売り手市場の状態が続いています。これは、以下の具体的な根拠や数値から明らかと言えます。
有効求人倍率の高さと求人数の増加傾向
厚生労働省のデータによれば、令和4年12月時点での医師・薬剤師などを含む有効求人倍率は2.32倍であり、全職種の平均有効求人倍率1.28倍を大きく上回っています。これは、1人の求職者に対して約2.3件の求人が存在することを示しており、医師の需要が非常に高いことを示しているでしょう。
厚生労働省の「令和2年度職業紹介事業報告書の集計結果」によると、令和2年の常用求人数(有料・無料職業紹介事業合わせて)は約34万件、臨時日雇求人数は約156万件に上ります。同年12月31日時点の国内の医師数が339,623人であることを考慮すると、医師の人数を上回る求人数が存在しており、市場規模の大きさが伺えます。
少子高齢化と地域による医師不足の偏在
さらに現在の日本の医師求人市場は、医師の地域偏在や少子高齢化に伴う医療需要の拡大により、常に売り手市場の状態が続いています。特に地方の医療機関では医師不足が深刻であり、有効求人倍率が8倍近くに達する地域も存在。都市部に医師が集中する傾向が影響し、地方の病院やクリニックでは高待遇での採用を進めるなど、人材確保に向けた対策が取られています。
また、高齢化社会の進行により医療サービスの需要は増加し、慢性的な人材不足が続いていることも、医師の求人が活発である要因の一つです。さらに、近年の働き方改革によって医師の労働環境改善が求められ、医療機関の採用ニーズは一層高まっています。
加えて診療科によっても求人状況は異なり、内科・外科・救急科などは安定した募集がある一方、小児科や形成外科などでは比較的求人が少ない傾向にあります。こうした背景から、医師の転職市場は流動性が高く、求職者にとって選択肢の幅が広がる環境が整っていると言えるでしょう。
医師業界の求人待遇は個人によって大きく変動
医師の求人市場において、専門医資格の有無や臨床経験、診療科の違いは、受けられる求人の待遇に大きな影響を与えます。特に、専門医資格を持つ医師は、高収入・好条件の求人に応募できる機会が増える傾向にあります。例えば、麻酔科専門医や救急科専門医は全国的に需要が高く、高待遇での採用が期待できます。また、内視鏡や画像診断などの専門スキルを持つ医師も、専門クリニックや病院からのオファーが多く、選択肢が広がるでしょう。
一方、診療科ごとの求人状況にも違いがあり、外科や救急科は即戦力としての経験が重視され、給与面での優遇が受けやすい傾向にあります。一方で、小児科や精神科では医師不足が深刻な地域が多く、地方の医療機関では高額な年収や住宅補助付きの求人も多いのが特徴です。
より良い待遇の求人を見つけるためには、市場の動向を把握し、自分のスキルや経験に合った職場を探すことが重要です。76,000人以上の医師転職を支援してきた実績を持つ「医師転職ドットコム」など、医師特化の転職サービスが保有する具体的な求人を調査しながらポテンシャルを図ってみるのもありでしょう。
\ 医師転職なら業界実績No.1! /
【ブラックすぎ】医者が激務は嘘か本当か:まとめ
医師は激務といわれることが多いですが、実際の労働環境は診療科や勤務先によって大きく異なります。救急科や外科などでは長時間労働や不規則な勤務が常態化している一方で、皮膚科や眼科、健診センター勤務などは比較的安定したスケジュールで働けるケースもあります。また、大学病院では研究や教育業務が加わるため負担が増えることがある一方、民間病院やクリニックでは業務内容がシンプルになり、働きやすい職場も存在します。
このように「医者=激務・ブラック」というイメージは一概には言えず、労働環境の良し悪しは職場次第です。現在の職場に不満を感じている場合、診療科の変更や転職によってより働きやすい環境を見つけることも選択肢の一つとなります。
もし、今の働き方に疑問を感じているなら、実績のある医師特化型転職サービスを活用することで、自分に合った職場を効率的にリサーチするのもあり。より良い働き方を実現するために、一度専門の転職支援を受けてみることもおすすめですよ。
\ 医師転職なら業界実績No.1! /
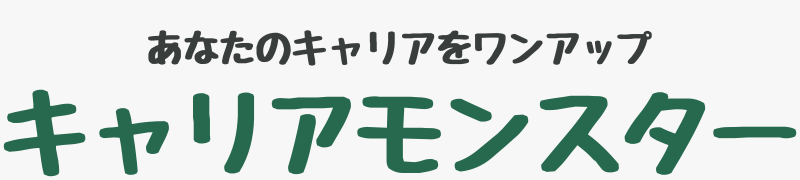









コメント